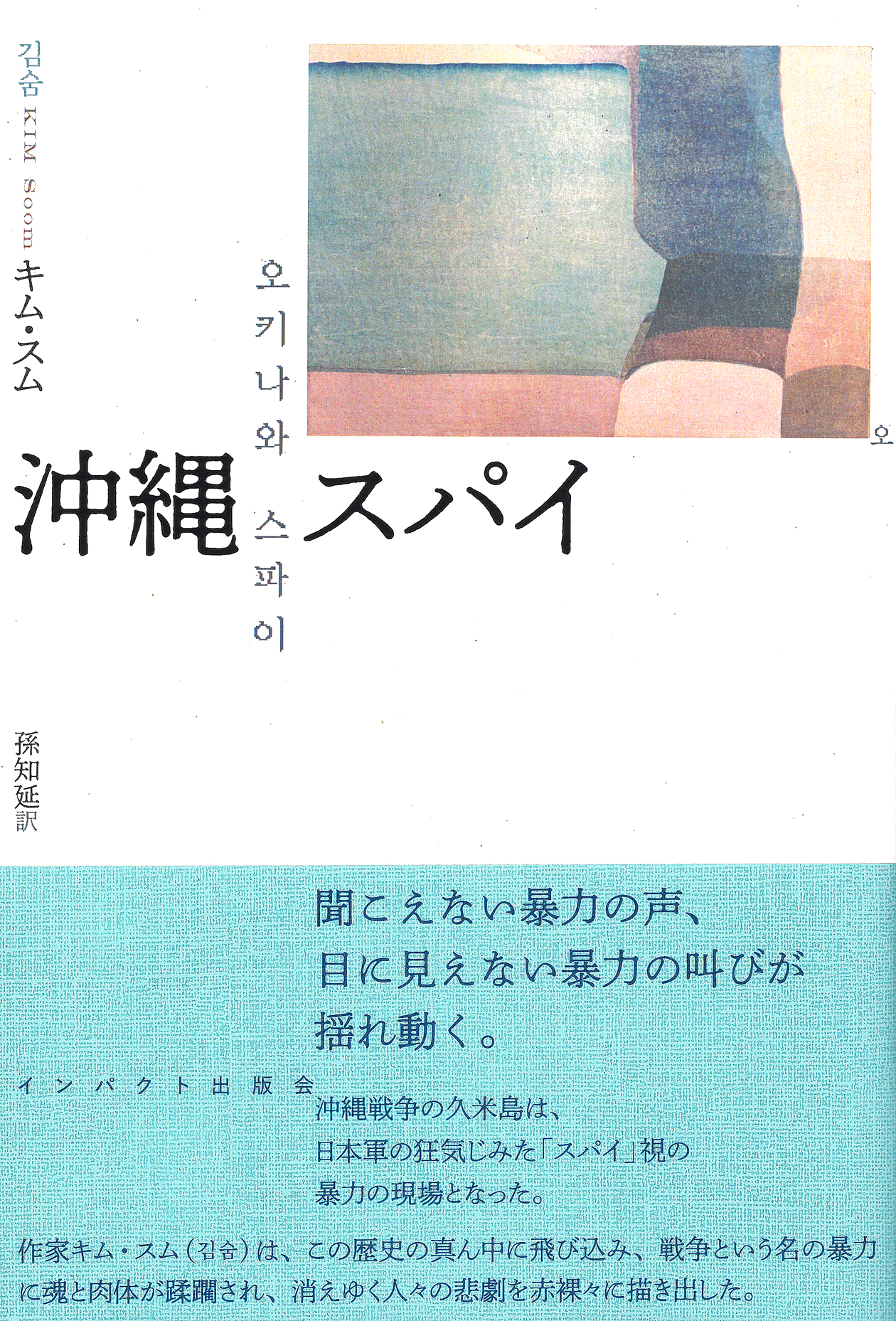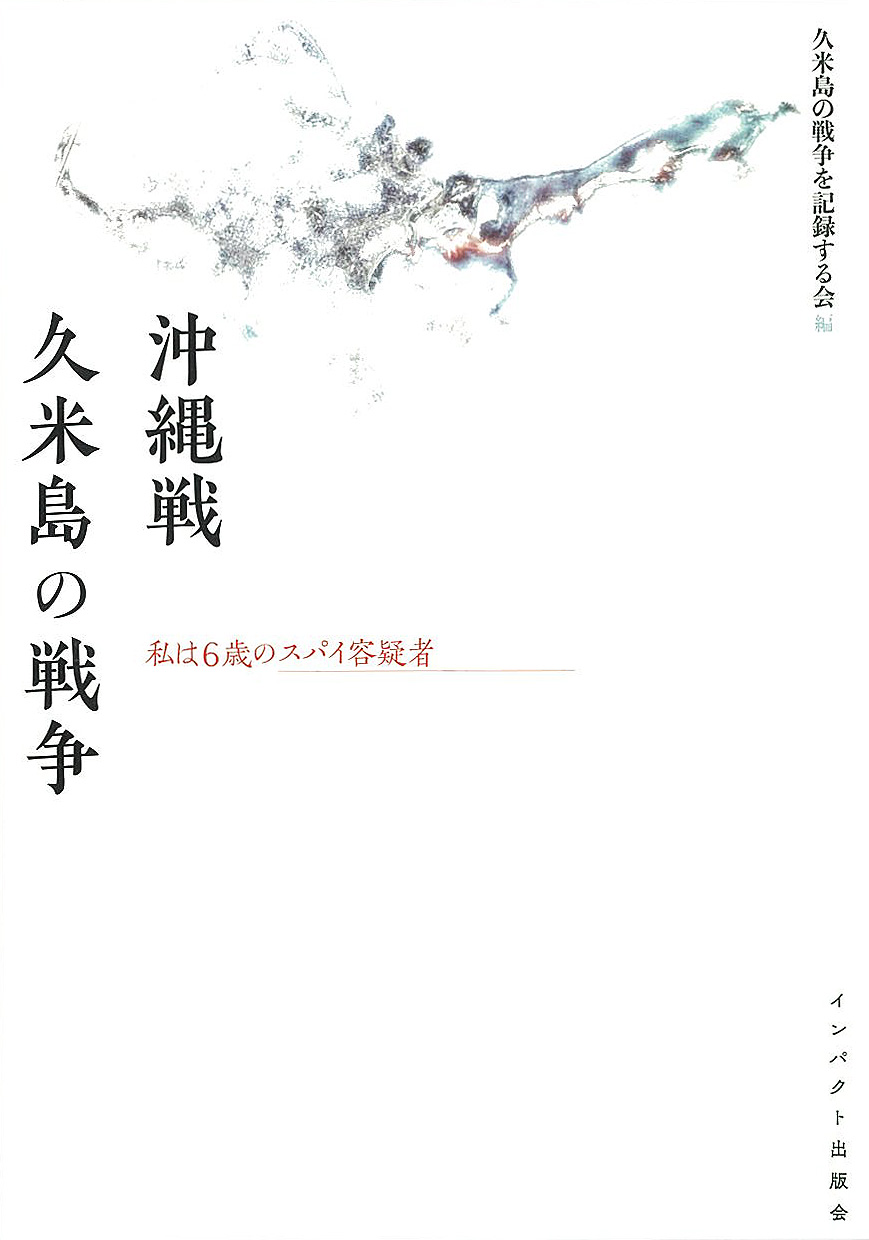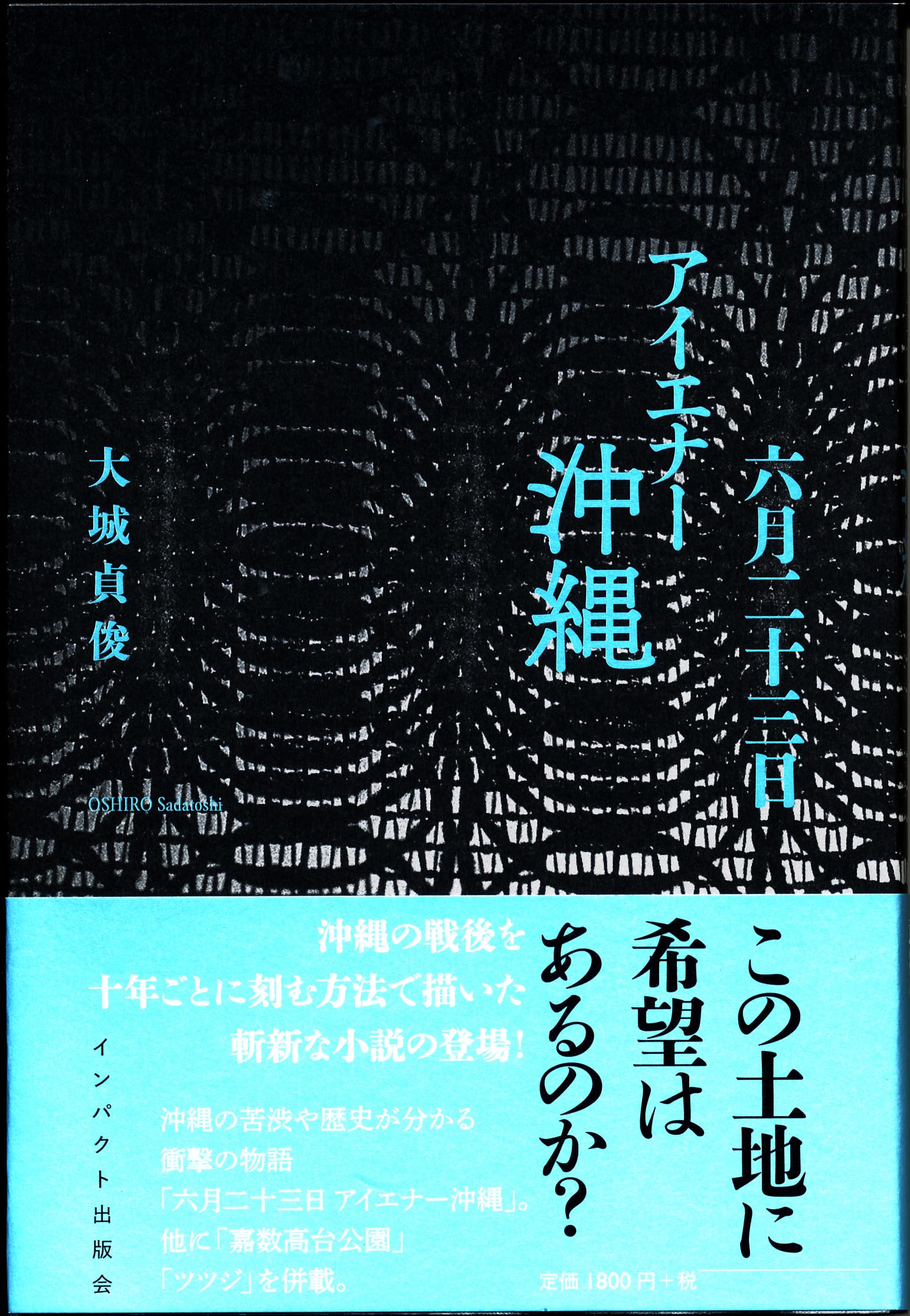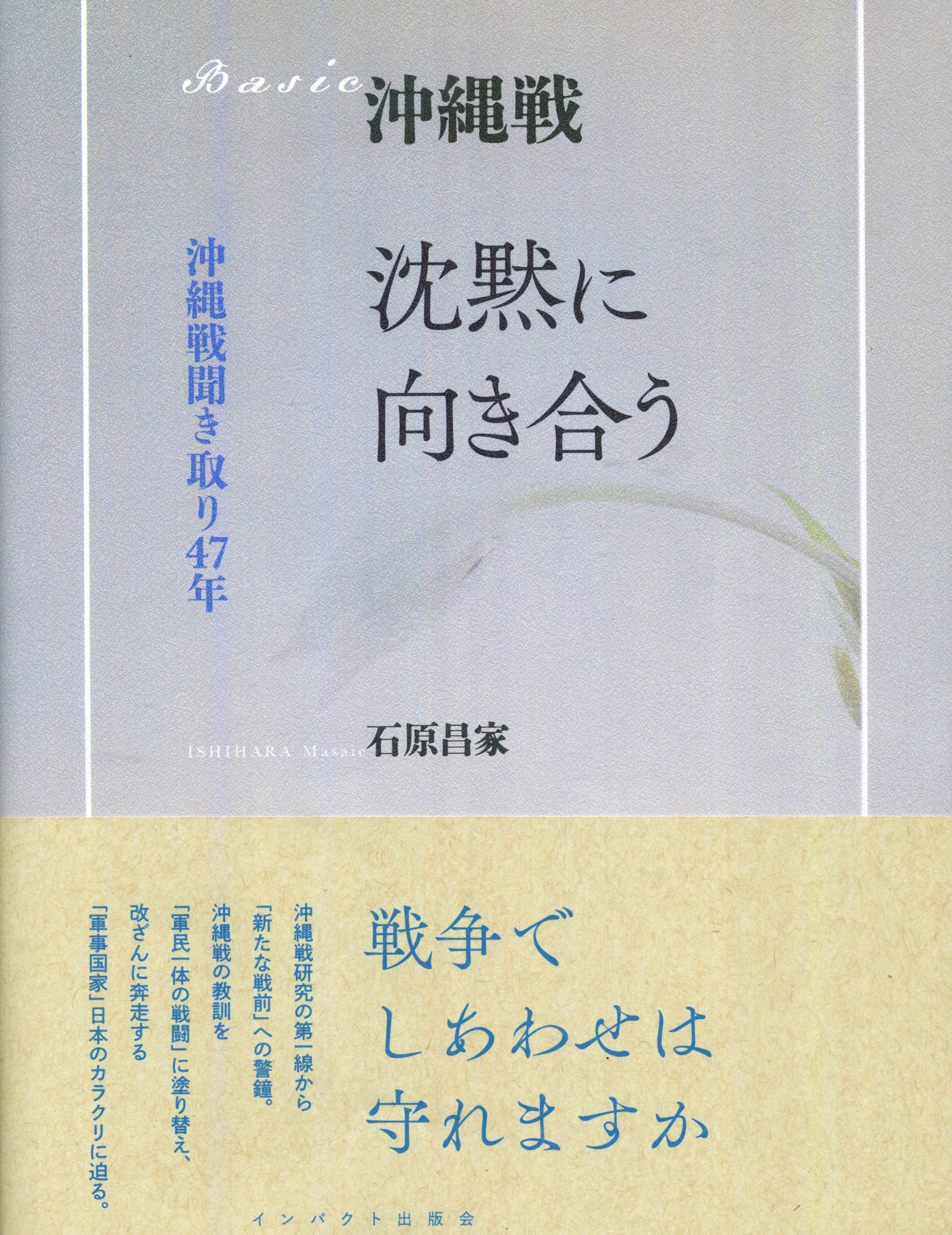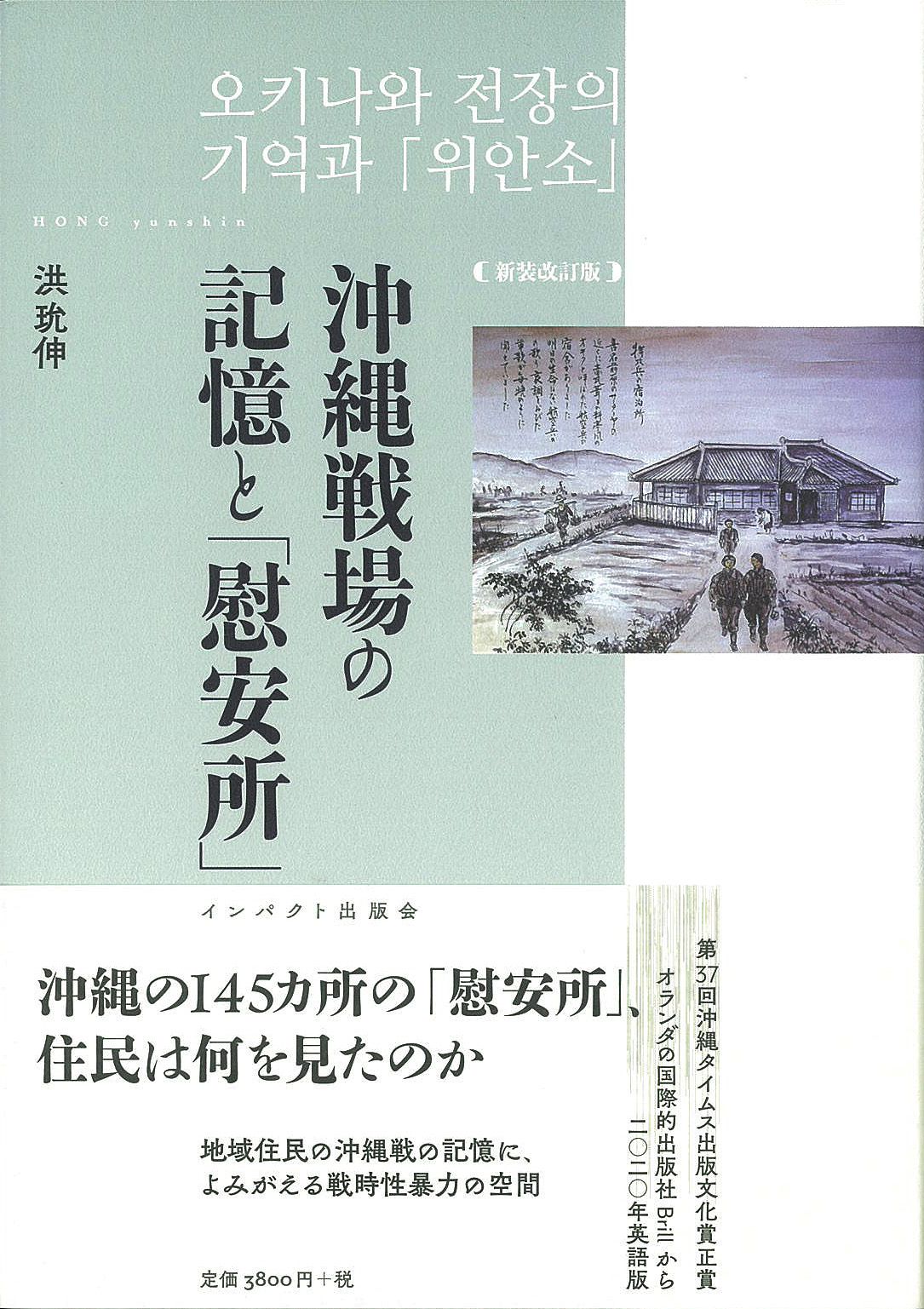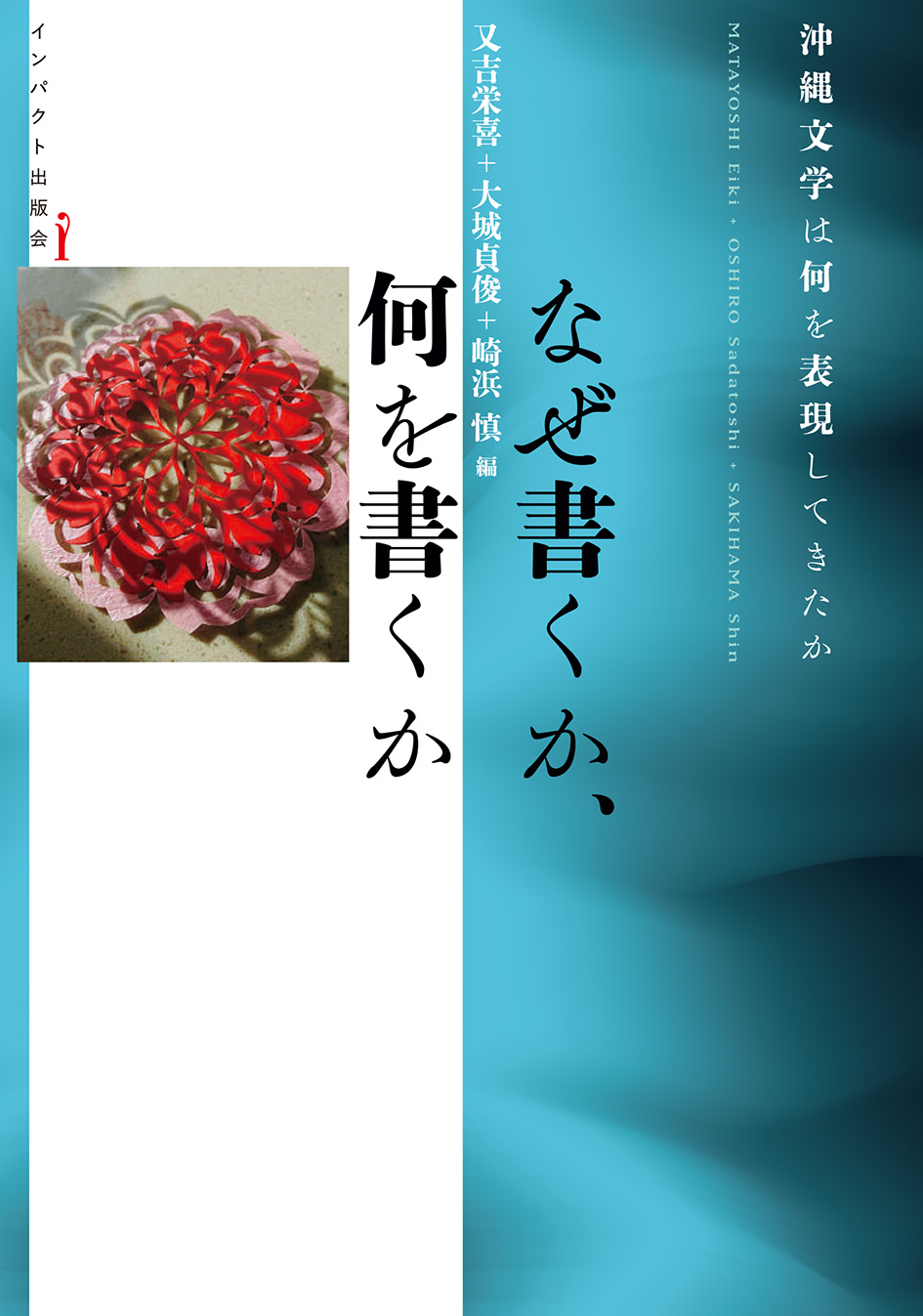沖縄 スパイ
沖縄戦争の久米島は、日本軍の狂気じみた「スパイ」視による暴力の現場となった。20人の住民がスパイ容疑で虐殺され、敗戦後の8月20日には父親が朝鮮人の家族7人が虐殺された。作家キム・スムは、この歴史の真相に飛び込み、軍国主義の狂気に向き合って、消えゆく人々の悲劇を赤裸々に描き出した。
原題『오키나와 스파이(沖縄 スパイ)』(モヨ社、2024.7)
<訳者による作品紹介>
この小説は太平洋戦争当時、沖縄本島西側の小さな島、久米島で実際に起きた残酷な虐殺事件を描く。日本軍が善良な住民20人を「米軍のスパイという罪名で無残に殺害した「久米島守備隊住民虐殺事件」が小説化されたのは今回が初めてとなる。これまで日本でも、そして沖縄文学界でも取り上げられたことがない。
キム・スムはこの小説を書くにあたり膨大な参考資料を読み込み、久米島をはじめ、沖縄の多くの場所を幾度も訪れた。様々な作品で彼女が絶えず描きつづけてきた、見えない過去(歴史)を現在に召還し、再現しようとする「記録と「証言」の文学的実践である。彼女はこの小説で、日本帝国の狂気じみた暴力が、人間の基本的人権を蹂躙した歴史の現場に正面から向き合う。
この島では、様々な暴力が複雑に折り重なって存在した。日本軍の一次的暴力が横行し、住民の間にも「スパイ恐怖症」が呼び起こした様々な暴力が混在した。10代の幼い少年たちが、軍国主義思想に魂を奪われ、罪のない住民たちにスパイ容疑をかけて殺戮する姿は、想像もできないような暴力の極悪さを示している。聞こえない暴力の声、目に見えない暴力の叫びが揺れ動く。作家キム・スムは、この歴史の地層の真ん中に飛び込み、戦争という名の暴力に魂と肉体が蹂躙され、消えゆく人々の悲劇を赤裸々に描き出す。
沖縄を代表する作家、大城立裕や目取真俊が描く作品世界とはまた異なった、彼らが捉えきれなかった沖縄戦の実状が隅々まで暴かれる。
キム・スム特有の繊細な筆致が目を引く作品であり、戦争の裏側に位置する沖縄の日常空間(木、森、方言、食べ物、伝統、風俗など)に対する写実的描写が実に興味深い。
真藤順丈の『宝島』(講談社、2018)、高山羽根子の『首里の馬』(新潮社、2020)のように「沖縄」をテーマにした小説が直木賞、芥川賞などを受賞し、日本文壇の注目を集めた。キム・スムの最新作『沖縄スパイ』もまた、韓国小説に魅了された読者層のみならず、沖縄と東アジアのジェンダー問題に関心を持つ人々まで、実に幅広い読者層を惹きつけるであろう。
<著者紹介>
キム・スム (김숨) KIM Soom
1974年蔚山生まれ。97年「大田日報」新春文芸に当選、98年文学トンネ新人賞を受賞し、文壇デビュー。現在、韓国で最も注目される小説家の一人。現代文学賞、大山文学賞、李箱文学賞などを受賞。著書に短編集 『ベッド』、『肝臓と胆嚢』、『私は木を触ることができるだろうか』などの長編小説に加え『鉄』、『針仕事をする女』、『Lの運動靴』、『ひとり』、『流れる手紙』、『軍人は天使になりたいと願ったことはあるだろうか』、『崇高さは自分をのぞき込む』、『さすらう地』、『聞き取りの時間』、『ツバメの心臓』、『失った人』 などがある。邦訳作品に『ひとり』(岡裕美訳、三一書房、2018)、『さすらう地』(岡裕美訳、新泉社、2022)、『Lの運動靴』(中野宣子訳、アストラハウス、2022)がある。
訳者・孫知延(ソン・ジヨン)
慶熙大学日本語学科教授。慶熙大学グローバル琉球・沖縄研究所長。名古屋大学で日本近現代文学を専攻し、博士号取得。単著に、『戦後沖縄文学の読まれ方 ージェンダー、エスニック、そしてナショナル・アイデンティティ』、共著に、『冷戦アジアと沖縄という問い』、『戦後沖縄文学と東アジア』、『沖縄を求めて 沖縄を生きるー大城立裕追悼論集』、『Women in Asia under the Japanese Empire』などがある。『眼の奥の森』、『大城立裕文学選集』、『うんじゅが、ナサキ』、「ヌジファ」、「六月二十三日 アイエナー沖縄」、『首里の馬』などの小説を翻訳した。
<韓国主要メディアでの紹介文>
*死力を尽くした「文学的な目撃談」
この小説は、キム・スムのこれまでの作品とは全く異なる。例の文学的グロテスクではなく、惨状の一コマ一コマを動員可能なすべての言語で、死力を尽くして描写する。穏やかな一日の始まりを告げたかと思いきや、次のページをめくると死んでいる。沖縄戦の戦死者ではない、朝鮮人の民間人虐殺被害者を初めて国内文学で取り扱い、それを描ききっている。
大江健三郎は「日本の(矛盾した)現実を最も明確に示しているのが沖縄問題」だと指摘した。広島の原爆でその年に死亡した人(14万人)よりも、1945年4~6月に沖縄で死亡した民間人の方がその数を上回る。沖縄を犠牲にして日本は平和を手に入れた。その構造に隠された朝鮮人の死は数万人に上る。しかし、これはあくまでも推定値に過ぎない。従って「疑問死」だと言えよう。人間の野蛮性、卑怯でありながらも尊厳な生命力は、虐殺現場から時計の針を初めまで巻き戻してみたところで、果たして納得できるものだろうか。それゆえに「疑問死」なのである。
ーー「ハンギョレ」、イム・インテク記者、2024.07.05.
*理由もわからずに死んでいった沖縄人たち、そこに朝鮮人がいた。
小説家キム・スムの視線はどこまで届くのだろうか。1970年代、中東でドルを稼いで帰ってきた父親たち、造船所での日雇い労働者、暴力被害女性のような人物から、日本軍慰安婦となった被害者、高麗人、そして動物を経て沖縄に至るまで。「技法の多彩さと視線の深さ(パク・ヘギョン文学評論家)を絶えず握りしめてきた彼女が、韓国人にとっては「加害者」にしか見えなかった沖縄人のなかから、歴史の桎梏の前に犠牲となった無垢な面々を掬い上げた。
ーー「韓国日報」、チョン・ホンイプ記者、2024.07.05
*知らなかった、知りたくなかった歴史···沖縄朝鮮人虐殺
作家は当時の記録と参考資料、数回にわたる現地取材を土台に、残酷な虐殺の現場と戦争の狂気が押さえつけてきた当時の歴史を再現する。(…)容赦なく晒される人間の残酷さ、犠牲者たちが経験した具体的な苦痛、息が詰まるほど締め付けられてくる軍国主義の狂気の再現に向き合うことは、読者も本能的に避けたいことではある。しかし、世界に対する絶望と人間性に対する懐疑の末に鮮明に残るのは、数字ではなく、具体的な犠牲者に対する哀悼、戦争の非人間性に対する切実な覚醒なのである。
ーー「京郷新聞」、パク・ソンイ記者、2024.07.12.
*加害ー被害『境界の島』沖縄...被害者だけの歴史はない
キム・スムの小説を文学評論家のキム・ヒョンジュンは「記憶復元作業」と定義した。新しい長編小説『沖縄 スパイ』(モヨサ)でも、キム・スムは第二次世界大戦中、沖縄で行われた民間人虐殺事件を見つめ、完全に分離できない被害と加害の境界を掘り下げる。それを通じて、被害者の記憶復元を超え、戦争に巻き込まれたすべての人々の記憶復元を試みる。
ーー「文化日報」、ジャン・サンミン記者、2024.07.17.
*キム・スム「人間・歴史に対する省察がなければ、誰でも加害者になり得ますよ
東アジアへと想像力を急速に広げてきたキム・スム作家が見た太平洋戦争期の久米島守備隊住民虐殺事件は一体どのような姿なのだろうか。なぜこの小説を書かなければならなかったのか。彼の作家的な旅路はどこへ向かうのだろうか。キム作家は今回の作品執筆のために多くの資料を読み漁り、久米島をはじめ沖縄を二度にわたって訪問し、現地の住民や関係者たちにインタビューを行った。これを通じて、狂気じみた暴力が生命と人権を惨たらしく蹂躙した太平洋戦争期の久米島へと読者を導く。
ーー「世界日報」、キム・ヨンチュル記者、2024.07.30.
原題『오키나와 스파이(沖縄 スパイ)』(モヨ社、2024.7)
<訳者による作品紹介>
この小説は太平洋戦争当時、沖縄本島西側の小さな島、久米島で実際に起きた残酷な虐殺事件を描く。日本軍が善良な住民20人を「米軍のスパイという罪名で無残に殺害した「久米島守備隊住民虐殺事件」が小説化されたのは今回が初めてとなる。これまで日本でも、そして沖縄文学界でも取り上げられたことがない。
キム・スムはこの小説を書くにあたり膨大な参考資料を読み込み、久米島をはじめ、沖縄の多くの場所を幾度も訪れた。様々な作品で彼女が絶えず描きつづけてきた、見えない過去(歴史)を現在に召還し、再現しようとする「記録と「証言」の文学的実践である。彼女はこの小説で、日本帝国の狂気じみた暴力が、人間の基本的人権を蹂躙した歴史の現場に正面から向き合う。
この島では、様々な暴力が複雑に折り重なって存在した。日本軍の一次的暴力が横行し、住民の間にも「スパイ恐怖症」が呼び起こした様々な暴力が混在した。10代の幼い少年たちが、軍国主義思想に魂を奪われ、罪のない住民たちにスパイ容疑をかけて殺戮する姿は、想像もできないような暴力の極悪さを示している。聞こえない暴力の声、目に見えない暴力の叫びが揺れ動く。作家キム・スムは、この歴史の地層の真ん中に飛び込み、戦争という名の暴力に魂と肉体が蹂躙され、消えゆく人々の悲劇を赤裸々に描き出す。
沖縄を代表する作家、大城立裕や目取真俊が描く作品世界とはまた異なった、彼らが捉えきれなかった沖縄戦の実状が隅々まで暴かれる。
キム・スム特有の繊細な筆致が目を引く作品であり、戦争の裏側に位置する沖縄の日常空間(木、森、方言、食べ物、伝統、風俗など)に対する写実的描写が実に興味深い。
真藤順丈の『宝島』(講談社、2018)、高山羽根子の『首里の馬』(新潮社、2020)のように「沖縄」をテーマにした小説が直木賞、芥川賞などを受賞し、日本文壇の注目を集めた。キム・スムの最新作『沖縄スパイ』もまた、韓国小説に魅了された読者層のみならず、沖縄と東アジアのジェンダー問題に関心を持つ人々まで、実に幅広い読者層を惹きつけるであろう。
<著者紹介>
キム・スム (김숨) KIM Soom
1974年蔚山生まれ。97年「大田日報」新春文芸に当選、98年文学トンネ新人賞を受賞し、文壇デビュー。現在、韓国で最も注目される小説家の一人。現代文学賞、大山文学賞、李箱文学賞などを受賞。著書に短編集 『ベッド』、『肝臓と胆嚢』、『私は木を触ることができるだろうか』などの長編小説に加え『鉄』、『針仕事をする女』、『Lの運動靴』、『ひとり』、『流れる手紙』、『軍人は天使になりたいと願ったことはあるだろうか』、『崇高さは自分をのぞき込む』、『さすらう地』、『聞き取りの時間』、『ツバメの心臓』、『失った人』 などがある。邦訳作品に『ひとり』(岡裕美訳、三一書房、2018)、『さすらう地』(岡裕美訳、新泉社、2022)、『Lの運動靴』(中野宣子訳、アストラハウス、2022)がある。
訳者・孫知延(ソン・ジヨン)
慶熙大学日本語学科教授。慶熙大学グローバル琉球・沖縄研究所長。名古屋大学で日本近現代文学を専攻し、博士号取得。単著に、『戦後沖縄文学の読まれ方 ージェンダー、エスニック、そしてナショナル・アイデンティティ』、共著に、『冷戦アジアと沖縄という問い』、『戦後沖縄文学と東アジア』、『沖縄を求めて 沖縄を生きるー大城立裕追悼論集』、『Women in Asia under the Japanese Empire』などがある。『眼の奥の森』、『大城立裕文学選集』、『うんじゅが、ナサキ』、「ヌジファ」、「六月二十三日 アイエナー沖縄」、『首里の馬』などの小説を翻訳した。
<韓国主要メディアでの紹介文>
*死力を尽くした「文学的な目撃談」
この小説は、キム・スムのこれまでの作品とは全く異なる。例の文学的グロテスクではなく、惨状の一コマ一コマを動員可能なすべての言語で、死力を尽くして描写する。穏やかな一日の始まりを告げたかと思いきや、次のページをめくると死んでいる。沖縄戦の戦死者ではない、朝鮮人の民間人虐殺被害者を初めて国内文学で取り扱い、それを描ききっている。
大江健三郎は「日本の(矛盾した)現実を最も明確に示しているのが沖縄問題」だと指摘した。広島の原爆でその年に死亡した人(14万人)よりも、1945年4~6月に沖縄で死亡した民間人の方がその数を上回る。沖縄を犠牲にして日本は平和を手に入れた。その構造に隠された朝鮮人の死は数万人に上る。しかし、これはあくまでも推定値に過ぎない。従って「疑問死」だと言えよう。人間の野蛮性、卑怯でありながらも尊厳な生命力は、虐殺現場から時計の針を初めまで巻き戻してみたところで、果たして納得できるものだろうか。それゆえに「疑問死」なのである。
ーー「ハンギョレ」、イム・インテク記者、2024.07.05.
*理由もわからずに死んでいった沖縄人たち、そこに朝鮮人がいた。
小説家キム・スムの視線はどこまで届くのだろうか。1970年代、中東でドルを稼いで帰ってきた父親たち、造船所での日雇い労働者、暴力被害女性のような人物から、日本軍慰安婦となった被害者、高麗人、そして動物を経て沖縄に至るまで。「技法の多彩さと視線の深さ(パク・ヘギョン文学評論家)を絶えず握りしめてきた彼女が、韓国人にとっては「加害者」にしか見えなかった沖縄人のなかから、歴史の桎梏の前に犠牲となった無垢な面々を掬い上げた。
ーー「韓国日報」、チョン・ホンイプ記者、2024.07.05
*知らなかった、知りたくなかった歴史···沖縄朝鮮人虐殺
作家は当時の記録と参考資料、数回にわたる現地取材を土台に、残酷な虐殺の現場と戦争の狂気が押さえつけてきた当時の歴史を再現する。(…)容赦なく晒される人間の残酷さ、犠牲者たちが経験した具体的な苦痛、息が詰まるほど締め付けられてくる軍国主義の狂気の再現に向き合うことは、読者も本能的に避けたいことではある。しかし、世界に対する絶望と人間性に対する懐疑の末に鮮明に残るのは、数字ではなく、具体的な犠牲者に対する哀悼、戦争の非人間性に対する切実な覚醒なのである。
ーー「京郷新聞」、パク・ソンイ記者、2024.07.12.
*加害ー被害『境界の島』沖縄...被害者だけの歴史はない
キム・スムの小説を文学評論家のキム・ヒョンジュンは「記憶復元作業」と定義した。新しい長編小説『沖縄 スパイ』(モヨサ)でも、キム・スムは第二次世界大戦中、沖縄で行われた民間人虐殺事件を見つめ、完全に分離できない被害と加害の境界を掘り下げる。それを通じて、被害者の記憶復元を超え、戦争に巻き込まれたすべての人々の記憶復元を試みる。
ーー「文化日報」、ジャン・サンミン記者、2024.07.17.
*キム・スム「人間・歴史に対する省察がなければ、誰でも加害者になり得ますよ
東アジアへと想像力を急速に広げてきたキム・スム作家が見た太平洋戦争期の久米島守備隊住民虐殺事件は一体どのような姿なのだろうか。なぜこの小説を書かなければならなかったのか。彼の作家的な旅路はどこへ向かうのだろうか。キム作家は今回の作品執筆のために多くの資料を読み漁り、久米島をはじめ沖縄を二度にわたって訪問し、現地の住民や関係者たちにインタビューを行った。これを通じて、狂気じみた暴力が生命と人権を惨たらしく蹂躙した太平洋戦争期の久米島へと読者を導く。
ーー「世界日報」、キム・ヨンチュル記者、2024.07.30.